京都ライター塾第4回目レポート
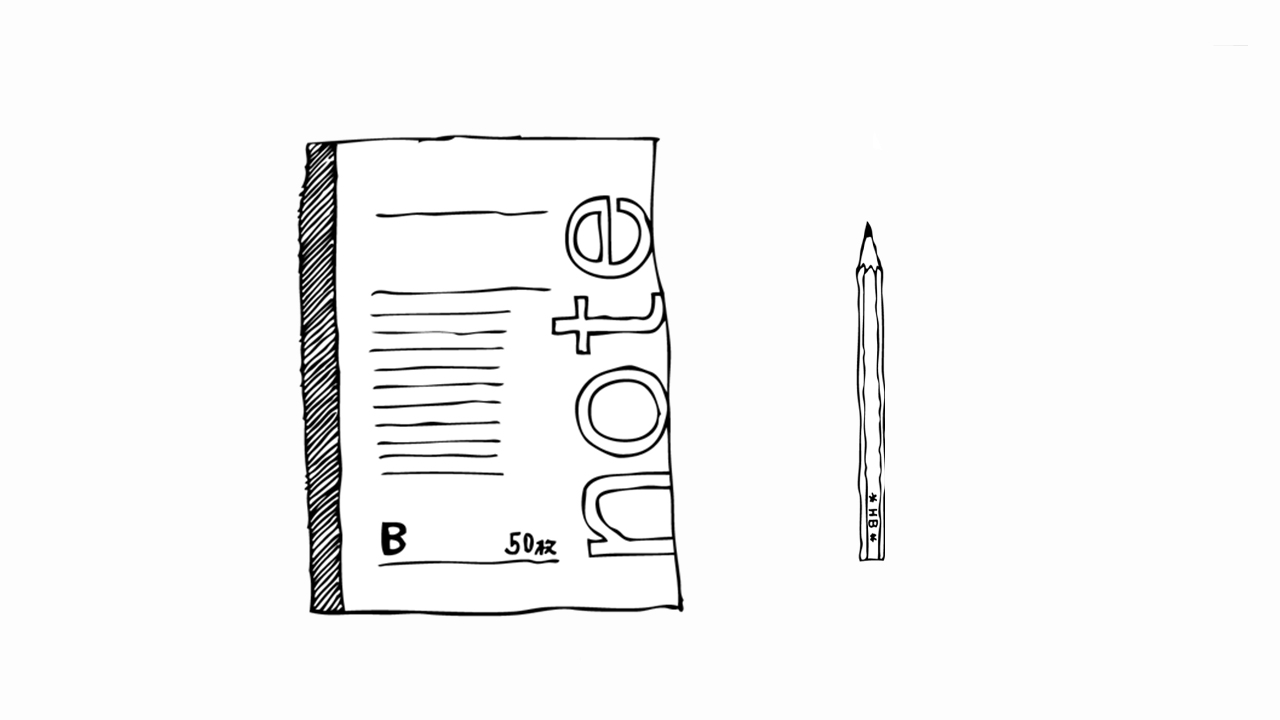
日付:2024年2月24日
江角悠子さん主宰
京都ライター塾の第4回目に出席。
前回提出した企画書のフィードバックと、インタビューの具体的なやり方について教えていただいた。
なぜ江角さんに聞くのか?を明確にする
まず最初は、前回の課題だった「江角悠子さんインタビューの企画書」の添削。
受講生10人が、思い思いのテーマで企画書を作った。
どんなテーマをみなさんが考えついたのかを見るだけでも、自分に無かった視点が学べておもしろい。
インタビュー企画を立てる上でなんと言っても大切だと痛感したのが「なぜ江角さんにインタビューするのか」を明確にすること。江角さんの特徴を挙げて、これについてぜひ江角さんに聞きたい!江角さんでなければいけない!!という内容にする必要がある。
実際の企画でも、そうしなければ取材相手に「私でなくても記事になるでしょう」と言われて断られる可能性も高い。
例えば企画書のタイトルや、原稿内容に入れる言葉。
単に「ライター」「お母さん」「読書好き」とすると、誰にでも共通する特徴になってしまう。パッと記事を見た読者にとっても、どんな魅力を持った人のインタビューなのかがわかりにくいし、興味も抱きにくい。
そこで「ライター18年目」「私設図書室を持つ」「わたしは、まじめちゃん。の作者」など、江角さんを象徴するような言葉を入れることが大切だ。
またインタビューを読むことで、読者にどんなメリットがあるかを考えておくことも大切。
例えば江角さんが日々おこなっている「発信」。
それをテーマに記事を書く時、もしかすると読者の中には「まだ発信をしたことのない人がいるかもしれない」ということに気づけるかどうかで、内容が変わってくる。
継続するコツや、ネタの探し方だけではなく、発信を始めることで仕事や人生が楽しくなるという切り口で書くこともできる。
読者に「私も発信してみよう!」と思ってもらうことが、江角さんにインタビューをする意義にもなる。
「この媒体に企画書を持ち込もう!」と決めたら、過去記事を読み込むことが最も大切だ。
もし似たような記事があれば、独自性が出るように変えてみたり、いいところがあれば真似してみる。
「ライターが過去記事を読み込んでいると、媒体側の人たちも嬉しいし、コンセプトに合っていると企画書も通りやすい」と話す江角さん。
取材相手にしても、媒体にしても、自分が関わりたいと思える興味のあることなので、調べるのも楽しい時間になり、メリットしかない!
インタビュー取材のやり方
「材」を「取」りに行くと書いて、取材。
ここでは、あるパン屋さんのまだ世に出ていない魅力を探りに行くことを想定して、具体的なやり方を一連の流れにしてまとめてみたい。
【取材対象となる人やお店を決める】
おいしそうなパンを売っている店を見つける。
【企画書を作る】
企画書に書くことは以下のようなもの。
・自分は誰か
(どこの媒体のライターか)
・媒体についての説明
(コンセプトや読者層、発行部数)
・取材をする目的を説明
・取材日時の提案
・撮影許諾のお願い
ここでは学んできた通り「なぜこのパン屋でなければならないか」を明確にすることが大切だ。
さらに事前に撮影したいものを伝えておくこと。「パンの写真を撮らせてほしい」と伝えれば、撮影用にパンを用意してくれるかもしれない。
写真を撮られるならきちんとした格好で写りたいという取材相手がいることも考えて「職人の写真もお願いしたい」と伝えておくと、スムーズに取材が進むだろう。
季節限定商品を撮影したい場合もある。雑誌などは発売されるかなり前に取材があるため、夏なのに「秋に販売される松茸パンは作れますか?」などと聞かなければいけないこともある。でも「撮影用に松茸、準備しておきますね」と言ってもらえるかもしれないので、必要なものについては一通り企画書で伝えておくのがよい。
【アポ入れ(メールを送る・電話する)】
江角さんの場合、まずはメールを送るそうだ。
「大変お忙しいと思いますが、いつまでにお返事を下さい」と添える。
そうすると、もし返事が来なかった時、電話をかける理由になるという。これは経験していないとできない工夫だ。
そして電話をかける際は、店が混んでいない時間帯を考えて、迷惑にならないようにすることが大切。江角さんは開店直後の、まだお客さんが来ていない時間帯を狙うという。
さらにGoogleで店を検索すると、混んでいない時間帯がグラフで出てくるので、それを参考にするという裏技も教えてもらった!!
【質問リストを作る】
店についての基本情報を押さえ、どんな原稿を書きたいかを決めておく。そしてできるだけたくさんの質問を考える。
例えばサンドイッチを取材したいなら、具を知っておくこと。食べに行った人のブログを読めば情報収集もできる。
情報が溢れている時代なので、ネットで検索すればその店の情報がすぐ出てくることもあるが、まだ誰も書いていないことを取材しに行く気持ちで臨むこと。自分の目で見て感じることで、ほかの人が書けないような記事になる可能性は大いにある。取材相手の下調べをしっかりして、誰も知らない魅力になりそうな特徴を見つけられるかが、ライターの素質として大切なことだとも言える。
作った質問リストは、事前に取材相手に送っておくと、インタビューされる側も答えや資料を用意しておけるので安心できる。確かに自分がインタビューされる立場なら、絶対リストがほしい。
【インタビュー当日の流れ・出発前】
持ち物確認!!
・音声レコーダー
・ペン(江角さんは3色)
・ノート(カバーがあって立ったままメモできるものがいい)
・カメラ(撮影用・自分のメモ用)
・名刺
・営業ツール(フリーペーパーなど)
江角さんは3000字を超える原稿を書く場合に音声レコーダーを使うという。2つ持っていくなど、人によって様々な取材の工夫がある。
さらにレコーダーには、持って行くと取材相手が緊張して「きちんと話さなければ!」と思ってもらえる裏技的な効果があるそうだ!
営業ツールとしてフリーペーパーを作って持参していたという江角さん。それを見た取材先の方が「うちもこういうの作りたい!」と言ってくれ、取材とはまったく違った新しい仕事につながったこともあるそうだ。仕事というのはどこに転がっているかわからないものである。
【インタビュー当日の流れ・取材先に到着】
身だしなみを整えて、いざ取材先へ。
店に到着したら、言葉遣いにも気をつけよう。
自分は「フリーライター」として、雑誌やweb媒体などに原稿を納品する立場で活動していたとしても、取材相手からは「月刊◯◯の人」などと媒体の人間として見られている。自分の態度や言葉遣いが悪ければ「月刊◯◯の人は最悪だ」と、媒体の名を傷つけることにもなりかねないので、看板を背負って取材に来ているという気持ちを持つことが大切だ。
インタビューする前には、取材相手と流れを確認する。
・改めてインタビューする目的を共有
・インタビューの段取りを決める
・録音の許可を取る(ここで裏技発動)
取材には編集者が同行せずライターに全てを任せられることも多いので、きちんと段取りを組めるようにしておくことも大切。
江角さんの取材パターンは、まず話を聞いてから、次に撮影。事前に調べてきたことに加え、当日インタビューの中に出てきたものも写真に撮りたいので、撮影を後に段取りしておくのがいいそうだ。
【インタビュー開始・終了後の確認事項】
録音とメモを取りながら、話を聞く。
次に、撮影。
聞くことを聞いて、撮るものを撮れば、取材は終了。
ここでかなり大切なのが、書いた原稿をいつ確認してもらうのか、今後の流れを取材相手とすり合わせしておくこと。
原稿を確認する人が出勤している日をきちんと把握し、場合によっては個人のメールアドレスを教えてもらうこともあるそうだ。確認は2、3日の間に、とお願いする。
以上のような流れで、パン屋の魅力を五感で探って素材を手に入れるのだ。
話の引き出し方のコツ
自分で作った企画書を元に、先日実際に江角さんにインタビューをした。
終わった今思うのは、経験を積むしかないな、ということ。いくら座学で頭に叩き込んで、表面的には整った質問リストを作ったとしても、やはり取材相手は生身の人間。心と空気を読んで質問しなければ、いい素材は手に入らないということを身を持って学んだ。
講座で教えてもらった話の聞き出し方のコツを、インタビュー体験で感じたことを交えてまとめてみる。
【笑顔でいること】
私がインタビューでまともにできたのは、笑顔だけだと言ってもいい(笑)かろうじて「えずさん」と呼んで打ち解けやすい雰囲気を心がけ、とりあえず終始笑っていた気がする(もしかして引きつっていたかもしれないが。)
オーバーリアクションがいいという相槌は意識したが、もう少し激しくてもよかったかもしれない。笑顔で質問し、江角さんが答えている時には真剣な顔をするというメリハリをつけたつもりではあった。
焦ってもゆっくりと質問することが大切で、相手の話をさえぎらず沈黙にも耐える、というのが聞く姿勢のコツらしい。緊張してなかなかできなかったが、これは日常生活で練習できそうなので、意識して取り入れてみたい。
【細かく質問を分ける】
質問はもっと細かく分けるべきだったと、終わってから痛感した。
1つの質問に対して、自分が想像する答えの分量と、実際相手が答えてくれる分量は違う。細かくたくさん質問を作っていれば、必然的に答えの量=素材の量が増えることになる。
【聞いた話の中から、次の質問を考える】
泣きたいくらい、まったくできなかった(笑)
やはり基本的に「根掘り葉掘り聞きまくる!!だって話が聞きたいんだから!!答える義務もあるしね!!」みたいな貪欲さが足りなかったように思う。私のような、いつでも大きな不安ばかりが先に立つ人間は、ゲーム感覚くらいでないと物事が進まない。
貪欲さとゲーム感覚があれば「構成にある話が筋書き通り聞けなければ記事にならない!!」という不安を超える助けにもなると感じた。
大きな構成の柱は大切にしながら、目の前にいる取材相手を生で見つめて、おもしろそうな方向にどんどん話を脱線させていく。そのくらいの遊び心が持てるようになれば、インタビューが楽しいと思えるのかもしれないと、未来の自分を想像した。そうなれば記事も予定調和を超えた魅力的なものが出来上がるのだろう。
そして何より、入念な事前準備に尽きると感じた。準備は心の余裕を生む。鳥が一本一本小枝を集めてきて巣を作るように、いろいろな情報を蓄えて、大きな巣の中に座ってインタビューに臨むイメージ。自分の知らない木の丈夫な小枝=新しい素材が取材相手から手渡されたら、巣に加えてより強いものに作り直すことができるし「その小枝もっとください!」とおねだりもできる。
まずは土台となる巣作りをしっかりすること。緊張しやすく、心や空気を読むスキルの浅い自分には、このような地道な努力がまずは一番大切かもしれないと実感した。
まとめ
講座の中でも、実際のインタビューの中でも、「あなたに興味を持っています。ぜひあなたにお願いしたい」という真剣な姿勢を持つこと、そして相手に伝えることが、取材には大切だということが理解できた。
こんなに実践的な学びをさせてもらい、失敗する場を与えてもらったことに本当に感謝したい。
あと残り2回となった講座でも、たくさんのことを吸収していけたらと思う。
