京都ライター塾第5回目レポート
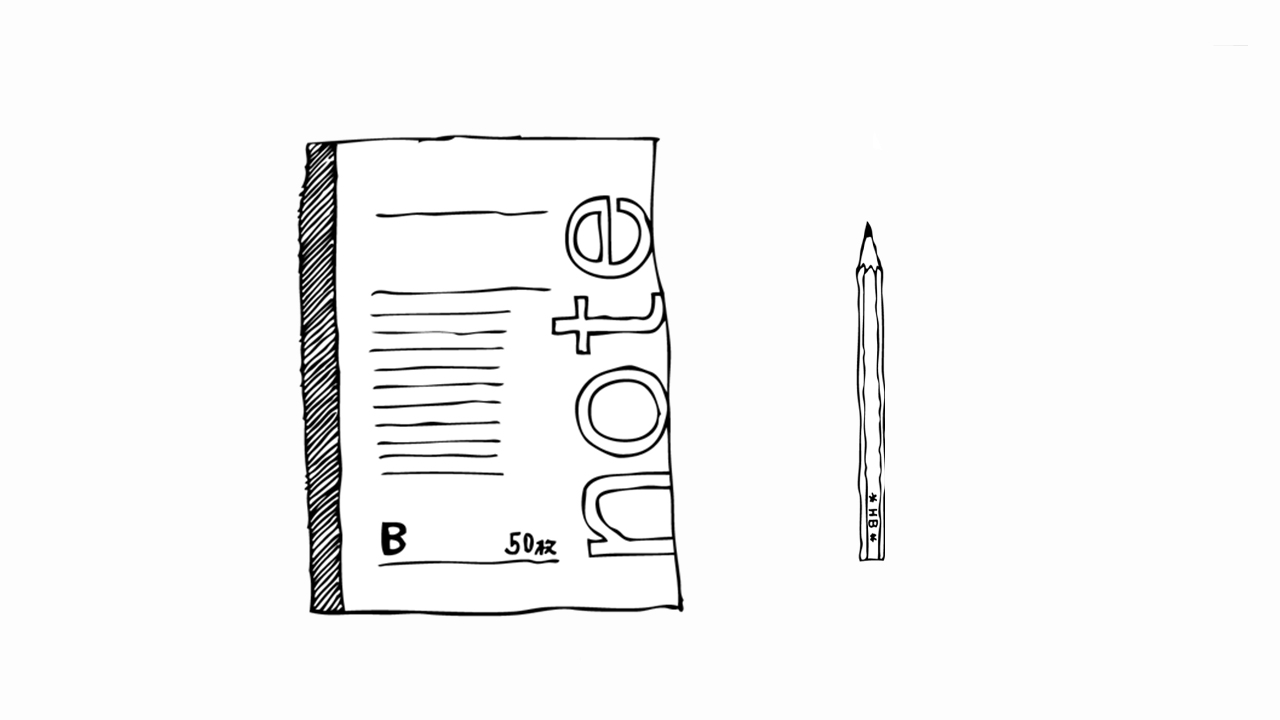
日付:2024年3月9日
江角悠子さん主宰
京都ライター塾の第5回目に出席。
前回の課題だった「江角さんインタビュー企画」の原稿を添削していただいた。
インタビュー原稿には手を加えること
商業ライターとして原稿を書くとき、基本的に大切なことは、誤字脱字をしないこと、同じ言葉を何度も使わないこと、口語を文語に置き換えること、読み手に推測させないことなどをこれまで学んできた。
このようなことを踏まえた上で原稿を作ったのだが、実際書いてみるとこれらを守りながら完成させるのは簡単ではないことを痛感した。
受講生に共通していた注意点は「インタビュー原稿にはもっと手を加えなければいけない」ということ。
例えば、江角さんがしゃべった話を、しゃべったまま書いてしまっている原稿が多かった。江角さんの話を軸に原稿を書くのだが、文字にするときは、真意がより伝わりやすいように言葉を補ったり書き換えたりする必要がある。
人は自分が苦労したことを話すとき、マイナスな表現を使わないと説明できないことも多い。苦労した原因が自分以外の人や物にあるならば、悪口に聞こえる場合もある。それはその人が感じたことであり決して間違いではないが、注意しなければいけないのは、聞いた言葉をそのまま書いてしまうと、取材相手が悪口やきつい物言いをする人のように見えてしまうこと。
そのマイナスな印象を与える言葉を、ポジティブに、マイルドに言い換えることが大事だそうだ。
「ブラック企業」→「やりがいはあるが勤務時間が長い」
「◯◯がおかしい」→「自分とは考え方が合わず悩んだ」
「◯◯を伝えるのに苦労した」→「アドバイスを続けた」
さらにポジティブな言葉にも、肉付けしていくことで取材相手が言いたいことが伝わりやすくなる。
「楽しいことがいっぱいある!」→「楽しいことがいっぱいありすぎて、答えに困る!」
こうして取材相手の魅力的な部分を読者に伝えていくために、工夫して文章を作っていくのがライターの仕事だと、初めてインタビュー原稿を書いてみて実感した。
「盛り上がった=書いていい」という恐ろしい勘違い
私が今回大失敗したのは、江角さんと旦那さんのエピソードをそのまま書いてしまったこと。
江角さんからの添削は、この書き方では読者にマイナスな印象を与えかねないので、書き直すか削除する方がいい、という内容だった。
なぜその話題をそのまま入れたか、真面目に言い訳したいと思う。
私の企画のテーマは「家事と育児を家族で分担して、母親が自分の時間を上手に作るコツを教えてもらう」というもの。
その中で旦那さんが、これまでやったことのない家事を担当してくれることになったときに、大変だったエピソードをうかがった。
女性と男性で家事や育児に対する認識に違いがあることは私も身を持って感じていたので、江角さんの話にはものすごく共感した。そしてインタビューの中で一番盛り上がったと感じたので、これは入れたい!と私は思った。
この話題を入れる選択に間違いはなかったと思う。
問題だったのは、その書き方。
問題点その1:
「江角さんが苦労した」視点だけで書いてしまった
家事を分担するのだから、江角さんも旦那さんもお互い大変だったはず。しかし私は話に共感するあまり、江角さんが苦労したという視点だけを原稿に書いてしまった。これでは旦那さんがどれだけ頑張ったかが読者にまったく伝わらない。それどころか悪口になりかねない。配慮と空気を読む力が足りていなかった。
問題点その2:
「盛り上がった=そのまま書いていいよ」というサインでは決してない
この話題が盛り上がったのは、インタビューという空間だったからこそ。
このエピソードが出る前にはいろいろな会話を重ねているわけだし、流れやノリというものがあって、盛り上がる場面があった、ということ。
この空気を体感できない読み手に対して、江角さんの話をそのまま言葉にしてしまっては、誤解が生まれるのも当然。
「これは夫に読ませられないな〜!」と言う江角さんの言葉を聞いて、私は恐ろしい勘違いをしてしまったことに気づいた。
問題点その3:
江角さんの口調を読者は知ることができないという認識が足りなかった
江角さんはゆっくりと話すし、声質も柔らかい。それに穏やかな雰囲気でとてもしゃべりやすい。話の間には、当時を思い出して丁寧に言葉を選んでいる様子もあった。
私には話を聞く以外にも、このような目と耳で得た江角さんについての情報があった。だから過去に本当に大変だった様子が伝わってきたし、旦那さんにも愛情を持って接していることが理解できた。マイナスな印象もまったく抱かなかった。
しかし江角さんのこの口調を、読者は知ることができない。その状態で、大変だったエピソードを江角さんの視点からのみそのまま書いてしまえば、確かに悪い印象になりかねない。
しゃべっている様子を見ながら聞くのと、ただ文字を読むのとでは、同じ話でもとんでもない差がある。その差を補うのがライターの仕事なのだと身を持って感じた。
改善策:
江角さんと旦那さんが協力して苦難を乗り越えたという表現にした
この話題を削除するより、夫婦でお互いに苦難を乗り越えたという表現に変えたいと思った。そこで「大変だった時期には、江角さんもサポートをしたし、旦那さんも根気よく新しい家事を覚えるために続けてくれた」という文章に書き直した。(現在添削待ち)
今考えてみると、こう書くのが当然ではないかと感じる。
自分が書いた原稿は、提出する前に寝かせた方がいい、と以前習ったはずだ。インタビュー後すぐに、熱が残った状態で書いたものをそのまま提出せず「本当にこのまま提出して大丈夫か?改めた方がよい言葉、内容はないか?」と、一旦冷静になって読み返す大切さを実感した。
その他よかった点:
まとめの言葉は、お子さんを大切に思う気持ちを最大限表現できた
原稿の最後は江角さんの言葉で締め、きれいにまとめてあると言っていただけた。
お子さんを大切に思う江角さんの気持ちは、短い言葉の中にものすごく詰まっていると感じられたものの、正直どう手を加えていいか迷った。私が言葉を書き換えたことで、すごく嘘っぽくなってしまったらどうしようと不安だった。
考えた末、とにかく読者に、江角さんから子どもへの愛情がまっすぐ伝わるようにと思って言い換えた結果、それは正しかったということがわかり、なるほど〜と思うと同時にホッとした。
インタビュー原稿で気をつけることまとめ
受講生10人分の添削を聞き、気をつけた方がよいポイントをまとめた。
【インタビュー後に作り変えていいものもある】
企画書で書いたタイトルは、インタビュー後により適した言葉や表現が見つかれば変更してもよい。また取材相手にした質問もそのまま書く必要はなく、より自然なつながりになるような質問にしてよい。
【文体は媒体に倣う】
。」←私はこの鉤括弧の前の句点を、書いていいのかよくないのかずっと悩んでいた。その答えは、媒体の過去記事にあった。大抵の場合、この句点はいらないらしい。このような細かいルールや漢字表記は、過去記事を読んで調べ、それに倣って書くことが必要だそうだ。
【「繊細」ということについて】
江角さんはよく、繊細な気質についてのことを文章に書いていて、それを読んで励まされることが私は多い。ただ、インタビュー内で自分のことを「繊細なので」と江角さんが言ったように書くと、「繊細だから気を遣ってよ」と言っているようにも受け取れてしまう。その場合「周囲の影響を受けやすいので」などと書き換える方がよい。
【並べると不自然になる肩書きがある】
江角さんには複数の肩書きや活動があるが、
「ツアーガイド・大学講師・お漬物講座」
と並べると、お漬物講座だけ浮いて見える。
もし並べるならば、
「ツアーガイド・大学講師・エッセイスト」
とすると自然に見える。
また「ときどき大学講師」というユーモアのある肩書きもあるが、これはプロフィールでは自然に見えても、原稿の中に入れると不自然になるので、やめた方がいいとのこと。
【「〜じゃないですか」多用問題】
この言い方は本当にいろいろな場面でよく聞くし自分でも使うけれど、原稿の中では使っても1記事1つにとどめること。
【完成原稿はプリントアウト・スマホで読む】
パソコン画面から一旦目を離し、紙に印刷したり、スマホ画面に映して原稿を読み直してみると、誤字脱字に気づきやすい。私もブログを書いたらスマホで一度読むようにしているが、この小さい画面に並ぶ文字だと、本当に誤字脱字や、この表現は変えた方がいいなということに気づきやすくなる。
このようにインタビュー原稿には「こんなに手を加えていいの!?」と思ってしまうほどの、伝えるための工夫がなされていることがわかった。
「世に出ているインタビュー原稿は、会話を切り取っただけのように自然に書いてありますが、実はどれだけ言葉を取捨選択して補っているかということが、わかってもらえたと思います」という江角さんの言葉に、本当に大きくうなずいた。
またマイナスをプラスに言い換えることができると、人生もポジティブになる!とも江角さんはおっしゃっていた。これは日常でも、優しく前向きな発見、思考転換をする練習になりそうだ。
プロフィール作りはむずかしい!!
次回はいよいよ、京都で対面の講座がある。
その際プロフィール写真を撮影することにしたが、この準備が初めてのことすぎて本当に戸惑った。
自分に似合う髪型も服もポーズもわからない。自分に似合うもの、好きなもの探しをサボってきたツケが今まわってきたように感じた。
髪型や服を必死に検索し、街では道ゆく人を観察。いくつも店に入って服を探すなど、いろいろやってみたが、結局行き着いたのはシンプルが一番ということだった。
どうやって自分をよく見せよう!?と無駄に考えていた自分に気がついた。
我に返ってシンプルな服を買おうとお店で悩んでいたとき、印象的なことがあった。
店員さんに「写真を撮る機会があって。。」と話したところ、「うちの服を着て写真を撮ってくださるということですね!」と目がキラキラと輝き出した。そして選んだ服を見ながら「この服は着たときに前に下がりやすいので」と、写真を撮る前に服を直すアドバイスを丁寧にしてくれた。
「写真を撮るために服を買う」なんて初めてだったので、そう伝えるだけでこんなに喜んでもらえるのか!と素直に驚いた。京都ライター塾は本当に最後まで、いろいろな場面で気づきがある。
さらに次回までの課題として、noteのプロフィール文も作らなければならない。
媒体によって、載せるプロフィール文を変えているという江角さん。旅好きな人が読む媒体なら、自分がどこへ行ったことがあるか、どんな旅が一番印象深かったか。お寺の檀家さんが読む媒体なら、自身の実家がお寺だということを書いているという。
これも私のプロフィール探しに基づけば、シンプルな書き方が大事なのだろうけれど、自分の好きなこと、やりたいことをシンプルに書けるだろうか。
講座は残すところあと1回。
最後までたくさんのことを吸収すると同時に、このライター塾が終わった後、路頭に迷わないように小さなことでも今から動き出したい。
