京都ライター塾第6回目レポート【最終回】
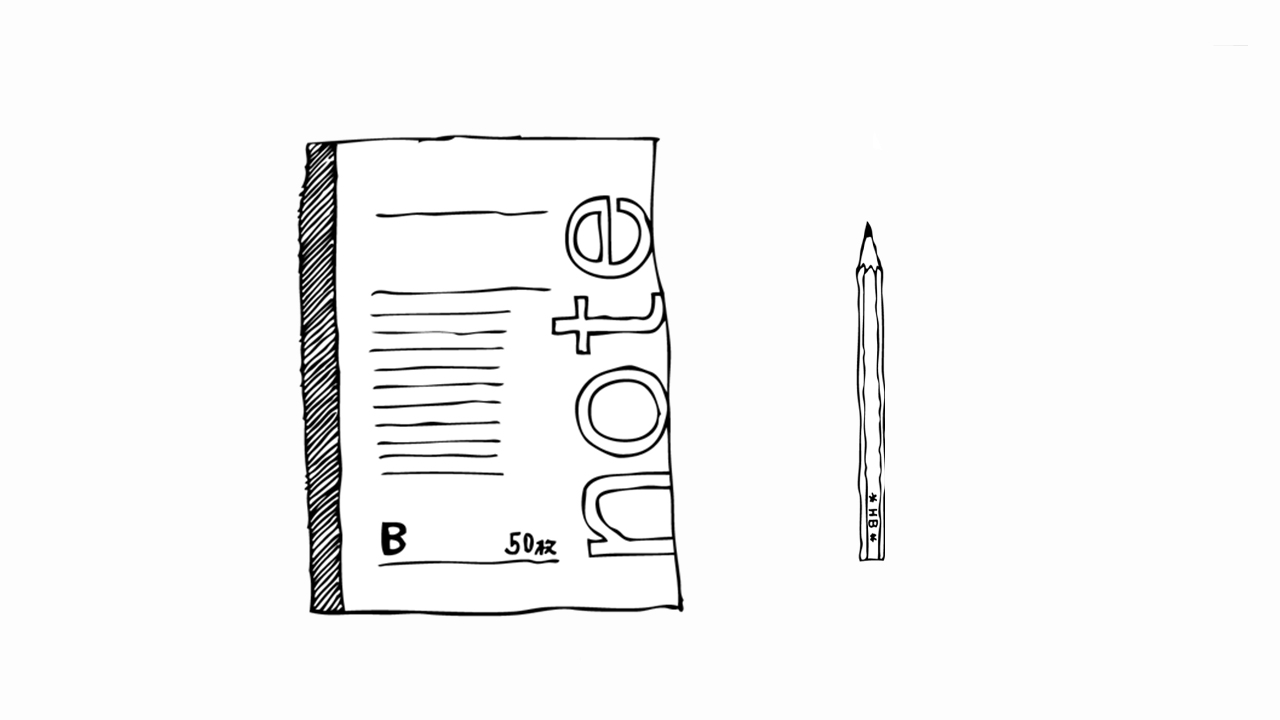
日付:2024年3月23日
江角悠子さん主宰
京都ライター塾の第6回目(最終回)に出席。
第5回目まではオンラインで学んできたが、今回は江角さんが活動の拠点としている京都で、初めての対面講座が行われた。
いつも最終回は対面で行われるのだと思っていたら、前回対面講座があったのはなんと1期生の時とのこと。2期生以降はコロナ禍になってしまい、オンラインのみとなっていたそうだ。
様々な業界から、同じ「書くこと」に興味を持って集まった方々。実際に会って交流ができるようになったこの時期に参加できたことを嬉しく思った。
今回のテーマは「新規仕事を得るための方法」
フリーライターという仕事をこれまでより具体的に学べた講座内容と、京都ライター塾自体のテーマである「幸せになる」ための生き方について、3ヶ月間でたくさんの気づきを得て考えたことをまとめたい。
フリーランスのメリット・デメリット
まずはフリーライターのメリット・デメリットについて、江角さんの経験談を交えて教えていただいた。
メリットは、
・時間を自分で管理できる
・好きな環境で作業できる
・子どもがいても働ける
・会社に依存しない
まもなく高校生になる息子さんと小学生の娘さんを育てる江角さんは、同じ年代の子どもがいる私にとって、少し先を歩く先輩のような存在。自分で仕事時間を増やしたり減らしたりしながら、子どもとの時間を大切にする仕事スタイルはとても参考になる。
またどんなに賃金や労働時間の条件がよくても、仕事がないのに職場にいなければいけないような会社では働き続けることができなかったという経験談にも大変共感した。限りある自分の時間。それをやりたいことに費やすためにも、フリーランスという働き方は意義のある選択肢だと感じた。
デメリットは、
・収入が不安定
・保証がない
・事務作業も自分でやらなければいけない
・一人で作業する孤独感
収入が不安定になるということで思い出したのが、2月の初めに家族でコロナに感染した時のこと。夫はなんと2週間近く陽性反応が出てしまい、その間出社することができなかった。それでも2月分のお給料を(少なくなったものの)いただけた時は、会社のありがたみを感じた。そんな夫は今の仕事とは違うことに挑戦したいという気持ちも持っており、もし夫婦でフリーランスになるとすると、収入の不安定さは覚悟しないといけないと改めて思った。
また中小規模企業共済というものを初めて知り、書くことだけでなくフリーライターとして仕事を続けていくために学ぶべきことはまだまだあると感じた。
煩雑な事務作業を会社がやってくれていたことも、フリーランスになって気づいたと話す江角さん。この話でも思い出したのが、最近私のミスが原因でやるはめになった、確定申告。やり方の解説を読んでもサッパリ意味がわからないし、何かの認証に数日かかることがいきなり判明したり、夫の会社から源泉徴収票をもらってきてもらわなければならなかったりと、追加の申告を少しするだけだったのにかなりの時間と労力がかかり、無事終わったら安心して体調を崩したほどだった。講座でもデメリットとして挙がるほどだし、こういうことはプロに頼った方がいいということなので、私もそれに倣おうと痛感した。
小さい仕事から実績をステップアップさせていく
仕事を依頼してもらうためには、自分がどれだけ文章を書けるかを目に見える形にしておく必要がある。
自分ですぐにできることは、
・公式サイト(ブログも可)を持つ
・実績を作る
・クラウドソーシングに登録する
フリーライターとして仕事をするなら公式サイトを持つといいと教えてもらってからブログを書くようになって、毎日投稿に挑戦し始めてまもなく2ヶ月になる。
しかし今回改めて教えてもらったのが、ブログを書いたらSNSなどで発信して読みに来てもらわなければ意味がないということ。私にはこれが足りていないと改めて感じた。
また私が一番知りたかったのが、実績の作り方。
0からライターを始めようと思ったら、まずは獲得しやすい小さい仕事をいくつかやること。それが10件くらい積み上がったら実績として自分の公式サイトに載せて、次のステップとして少し大きい仕事や、自分がやりたい仕事の獲得に繋げるために使っていくといいそうだ。
私は以前育児体験談を書くライターの仕事をしたことがあったが、次々と原稿を書くことを求められて体調を崩し、数ヶ月でやめてしまった。小さい仕事だったし、これが実績として役に立つとは思っていなかったが、積極的にこの経験も実績として使っていこうと思う。
仕事は「人」を介してやってくる
江角さんがライターになりたての頃は、売れっ子ライターが受けることができなかった仕事をもらうこともあったそう。現在でもライター仲間から仕事を紹介してもらうこともあるそうなので、人とのつながりはとても大切だということがわかる。目の前のやるべきことをきちんとしていると誰かがそれを見てくれていて、仕事につながりやすいというのはどの業界でも同じだと言えるだろう。
仲間を作ったら、やはりブログやSNSなどで文章を書いておくことが必要。ただこの時「自分が受けたい仕事に関係する文章を書いておくことが大切」と話す江角さん。
江角さんは京都ガイドの分野からライターの仕事が始まったそうで、当時ブログには観光に役立つ情報を多く投稿していたそう。その後、暮らしについての記事を書きたいと思うようになったものの、なかなか仕事にはつながらなかったという。
その理由はブログに、暮らしに関係する文章を書いていなかったからだった。確かに観光についてのブログを読んだ人が、「よし、暮らしについての記事執筆を依頼しよう」となることは考えにくい。(とレポートには簡単に書けるが、これは江角さんの経験から導き出された貴重な情報。これを教えてもらえることがとてもありがたい)
それに気づいてからブログの内容を変えていき、2年ほど経ってから仕事に結びついたのだそうだ。
江角さんほどのライターでも、自分のやりたい仕事を獲得するまでにはこんなに長い時間がかかるのだ。ライター初心者も夢中で書くことは大切だが、自分がやりたいテーマを早めに明確にして文章を書き溜めることが本当に大切だと言える。
「交渉」するためには根拠を添える
仕事をやることが決まった時の具体的な流れや動きも教えていただいた。
江角さんがライターになった頃は、このようなノウハウを教えてくれる人がおらず、クライアントとのスムーズなやり取りや確認しておくべきことはすべて経験から学ばなければならなかったし、賃金の交渉をしてよいことも知らなかったという。
【仕事の流れ】
①クライアントから仕事の依頼
(日時、拘束時間、締切日、予算などを確認)
②見積書を提出
(もしくは先方からの金額提示)
③取材
④原稿を執筆
⑤先方校正
(お店に原稿を確認してもらう)
修正があれば何度かやり取り
⑥納品
⑦入金
特に確認しておくべきことは、
・自分がする作業は何なのか
・取材先を探すことからするのか、取材先に行くだけでいいのか
・撮影は必要か
・どのくらいの間、取材先にいる必要があるのか
・原稿の締切日にはきちんと余裕があるか
(締切が翌日などということもあるので要注意)
そして金額交渉をする際のコツは、根拠も合わせて伝えること。
請ける仕事の分野ごとに、自分が何分で何文字書けるのかを計っておく。もし原稿を書く以外にも、取材先を決める作業や撮影があれば、いくらくらい金額を追加してほしいかということを明確にしておく。その上で「このくらいの仕事量であれば、自分はこれくらいの金額で請けたい」ということを相手に伝えると、納得してもらえる可能性も上がるそうだ。
江角さんが自分の希望金額を明確にするまでには長い時間がかかったという。
また、頑張ればこなせるのではないかと無理をしたり、次の仕事につながらなくなるのではないかという不安があり、自分が請けることがむずかしい仕事を断ることもなかなかできなかったそうだ。
このような気持ちの面での問題には心の底から共感した。私も別の場面で同じような状況になったことは多々あり、ライター業でも絶対に直面するはずだ。心構えをするとともに、このノウハウを積極的に活かしていきたい。
「やりたい!好き!」を具体的に伝えるプロフィール
前回出された、プロフィールを考えるという課題。
ブログ、note、Twitter、Instagramなど、プロフィールを書く欄が至る所にあってめまいがしそうになる。
私はとりあえず、趣味である仏像についての魅力や楽しみ方をnoteに書いていこうと思っているので、自称・仏像ライターとしてnoteのプロフィールを考えた。
ほかの受講生の方にもアドバイスされていたが、なんとなく雰囲気がいい言葉を書いても「それはつまりどういうこと?」と疑問が浮かんでしまうプロフィールはよくないという。
私の場合「手で作ったぬくもりのある仏像が好き」と書いていたら、江角さんに「仏像は全部手で作っているのでは?」と言われてしまった。これはまったくその通り。全部手で作られている中でも、どういう仏像にぬくもりを感じるのか、結局どんな仏像が好きなのかを言語化することが大切だとアドバイスをもらった。
それを元に、
「どうしてこういう姿に作ったんだろう?と、作り手に思いを馳せるのも好き。」
と修正した。(現在添削待ち)
ストレートに言語化すると、ちょっと不恰好だったり、ゆがんでいたりするような、いわゆる「ヘタウマ」みたいな仏像にひかれることが多い。でもこれをそのまま書くのはどうだろうという思いがあり、作り手に問いかけるような文章にしてしまった。添削を待ちながら、またいい言葉が思いついたら書き直して、自分らしいプロフィールを完成させていきたいと思う。
また仏像について話していたら「こんなに語れるなんてすごい」と言ってもらえたのはとても嬉しかった。仏像のことを文章にするなんてまったく考えていなかったので、新しい可能性が見つかってこれからが楽しみになった。
幸せに生きるための方法
京都ライター塾のテーマである「ライターになって幸せになる」
3ヶ月間をかけてライターのノウハウを学びながら、幸せに近づくための言葉を、江角さんにはたくさんかけていただいた。
講座が始まったばかりの頃の私には悩みが多く、雑談の中でそれを話すと
「嫌だと思うことに理由なんていらないんですよ」
「断ってもいいんですよ」
「まみさんは◯◯じゃないといけないんですか?」
など、自分のこれまでの凝り固まった考えをどんどん柔軟にしていく言葉をいただいた。
そのおかげで、もっと自分のやりたいことをやってもいいんだ、自分が幸せになるために行動していいんだと、とても前向きに物事を考えられるように変化していった。第1回目、第2回目あたりのレポートやノートを今読み返すと、どれだけ自分の考え方が変わってきたかがよくわかる。
また江角さんは人のよいところを引き出すのもとてもうまく、受講者がそれぞれ興味のあることややりたいことを発言する度に「いいですね!」と言ってくれた。(それを引き出した上で、どうやって伝わりやすい言葉で表現すればよいかまで教えてくれるところがありがたい!)
私の本業は動画編集だが、フリーランスとしてYouTube業界に入ってみたものの、人間関係がうまくいかなかったり、業界の雰囲気に馴染めなかったりして、体調を崩すようになった。体力的にも精神的にも限界がきて、動画編集者として働くことはもう諦めようと思って参加したのが、この京都ライター塾。
そこで思いがけず江角さんに、動画編集は需要があるからやってみてはと後押ししていただいたり、これまで見たことも編集したこともなかったInstagramの動画制作をする機会をいただいた。これは私にとって本当に本当に予想外すぎた出来事だった。編集ソフトをパソコンから削除しようと思っていたところだったが、江角さんのおかげで、まだ私にも学べることがある、仕事としてやれることがあるかもしれないと知って、本当に力が沸く思いがした。(崖から落ちそうになっていたところを引っ張り上げてもらえた心境)
私が苦しんだ場所と、力が沸いた場所。
この2つを比べてみると、人を尊重しないような場所で苦しみ、人の幸せを大切にする場所で力が沸いていた。
今初めて言葉にしてみると「そんなの当然じゃないか!」と驚いてしまった。
京都ライター塾で学んでわかった、私が幸せに生きる方法は「人」を大切にすることだった。
ライターなのか、動画編集者なのか、どちらをやるかということよりも(どちらもすごくやりたいこと)「一緒に仕事をしたい!」と思える人を大切にして、自分がやれることをやる。
そして自分が人に、同じように思ってもらえるよう成長すること。
これが私がこれから進んでいきたい道だと気づくことができた。
一人では決して気づけなかった、自分が幸せに生きる方法。
「書いて、しあわせになる」をテーマに活動する江角さんと、そのテーマに共感して集まったあたたかい同期のみなさんのおかげで、大変充実した3ヶ月を過ごすことができたことを、本当に感謝したい。
今後もこのご縁を大切にしながら、学んだことを活かして前に進んでいきたい。
