「質問の仕方」を子どもに教える大切さ
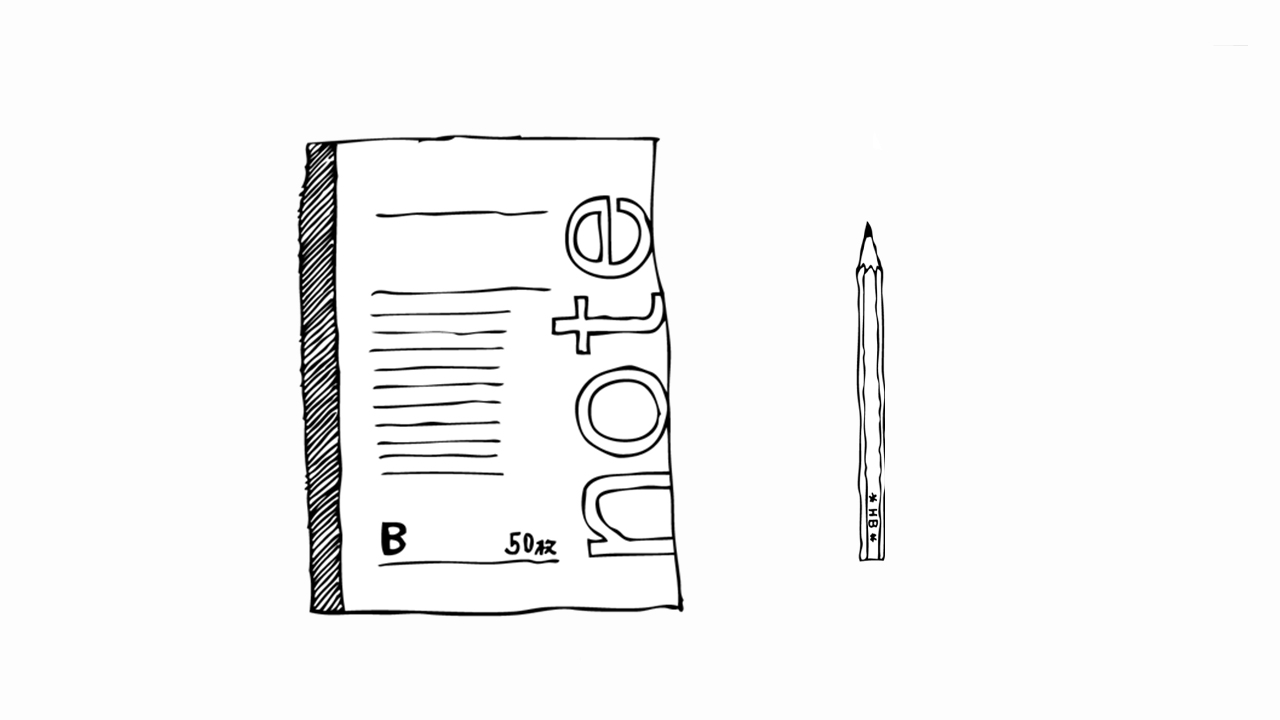
この春小学1年生になった娘。
今日は学校から帰ってくるなり
「あのね、
宿題忘れた人は
明日持って来てって言われた」
ほうほう。
確か昨日一緒に
確認した時は、
宿題はないって
言ってたような。
どうやら
宿題があることを
わかっていなかった様子。
「じゃあ
今日は宿題をやって
明日持って行こう。
で、宿題は何だったの?」
「え、わかんない」
ほうほうほう。
宿題があることは
わかったけれど、
それが何なのかは
確かめてこなかった、と。
娘は聞きたいことや
言いたいことがあっても
それを口に出せないで
黙っていることが
よくあるタイプなのです。
私も小さい頃
「こんなことを
言っていいのかな」
「聞くのが怖い」
ずっとそう思って
育ってきたので、
黙ってしまう気持ちは
痛いほどわかる。
でもそれでは
やるべきことをきちんと
できないばかりか、
「わからないなら
早く言いなさい!」と
怒られます。
(多々ある実体験)
さらに
言いたいことを
抑え込んでいるうちに、
自分の本当の気持ちが
まったくわからなくなって、
自分の思い通りでない
人生になってしまいます。
(実体験その2)
そして最近になって私は思いました。
子どもの時に
質問の仕方を
教えてほしかったな、と。
質問の仕方がわかれば、
聞くという行動の
ハードルが下がるはず。
これは今娘に
きちんと教える時だと思って、
わからないことは
きちんと先生に聞くことと、
「宿題は何ですか?」
「どのプリントを
出せばいいですか?」と
具体的に
質問の文言を教えました。
(ちなみに小6の息子は
何でもかんでも
先生に聞くタイプなので、
「自分はこう思いますが
これで大丈夫ですか?」と
自分の考えを添えて
質問するように伝えています)
質問の仕方によって
相手の答えも
変わってくるもの。
質問を積み重ねて
自分でうまい聞き方、話し方を
考えられるようになって、
「いい質問だね!」とか
「そういうことを考えているんだね。
ではこうしたらどうかな?」なんて
助言をしてくれる人に
出会えたら、
人生もいい方向に進むことが
あるかもしれません。
相手に手渡す質問によって
人生の行き先が変わってくる。
質問は世渡りの切符みたいな
ものだなと思いました。
