京都ライター塾第2回目レポート
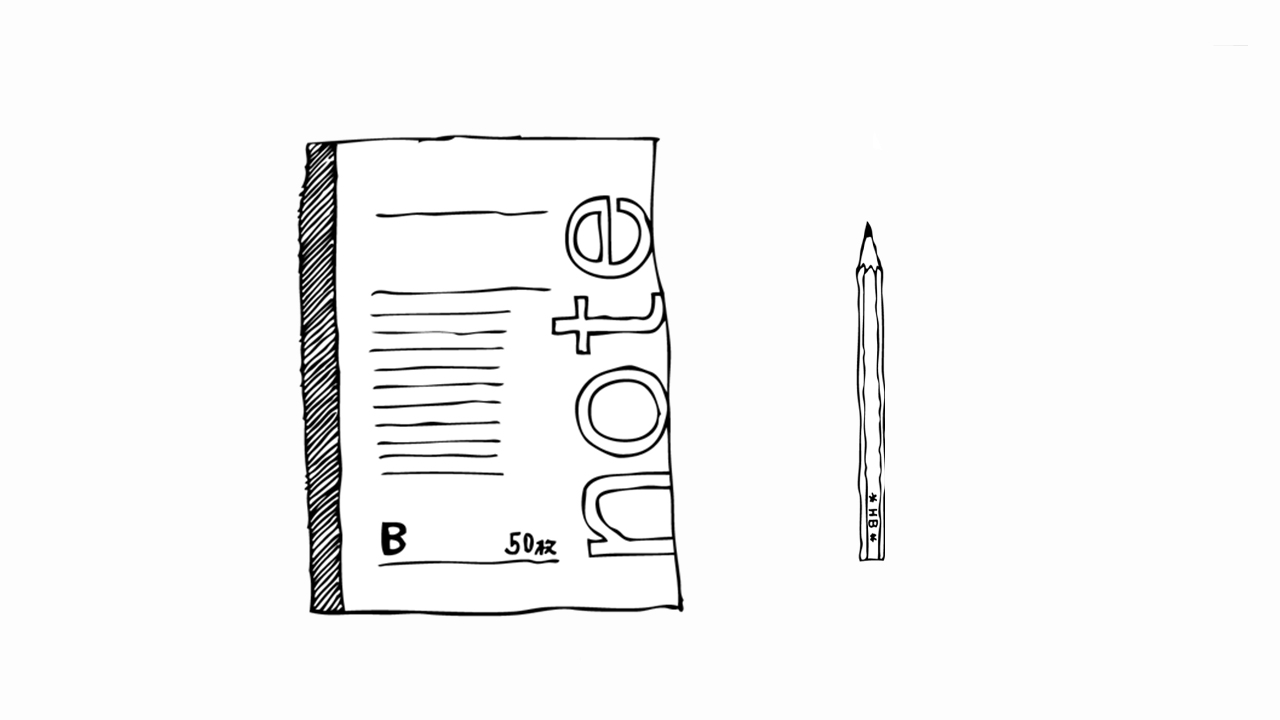
日付:2024年1月27日(土)
江角悠子さん主宰
京都ライター塾の第2回目に出席した。
今回のテーマは「インタビュー原稿の書き方」について。
インタビュー原稿とはどのようなものかや、理想の記事を書くための方法などを教えていただいた。
インタビュー原稿は素材が命
話を聞き出し、文章にしたものが「インタビュー原稿」だ。
インタビューと聞いて思い浮かぶのは、社長などから経営のヒント、苦労や生き方などを聞き出し、まとめるような雰囲気。
しかし意外だったのは、エッセイもインタビュー原稿だということ。
理由は、自分の思いを文章にするから。
「自分に話を聞く」ということだ。
実際自分の本を出版する際、自分に対してのインタビューを第三者にお願いし、それを録音したものを聞いてまとめ、本にすることもあるという。
さらにお店やスポットの紹介も、店員やスタッフに話を聞いて書くのでインタビュー原稿になるそうだ。
いずれも大切なのが、言いたいことをズバリと書くこと。
物語などとはちがって、読者に意図を読み取ってもらう必要はないそうだ。
文章が上手いか、美しいかよりも、わかりやすさが一番大事。
ということは、どれだけ詳細な情報収集ができるかにかかっている。
見て、聞いて、香りをかいで、さわってみて。
雰囲気を言語化する能力も必要だ。
人と会話する時、お店を訪れる時に「取材」だと思ってみると、情報を収集するアンテナをピンと立てる実践練習になりそうだ。
理想の記事を見つけて分解する
一つの記事を読んで、気づいたことを発表するワークが始まった。
「気づいたこと」という問いが難しい。
単に気づくことならいくつかある。
写真がきれい、場所とテーマが大きく書かれていてわかりやすい、建物の外観や内装の特徴がよくわかる、など。
頭を悩ませる受講者一同。
その中で現役ライターの受講者さんが、目次や全体を読んで、何がどういう流れで書かれているか、という構成を発表してくれた。
なるほど、必要なのは「書き手の目線」だったのだ。
読み手として内容を読むのではなく、書き手として構成を見る。
ここで、書き手目線になって行う、理想の記事を書く勉強法を教えてもらった。
まず「こんな記事が書きたい!」という記事を見つけて、それを分解してみる。
どういう構成になっているのか?何が書かれているのか?
ワークで学んだ通り、書き手目線になって調べてみる。
すると、どんな素材が必要なのか、わかってくるのだ。
例えば「ホテル紹介」の場合
・外観
・部屋の様子
・レストラン
・オプション
例えば「人物インタビュー」の場合
・現在何をしている人か
・過去に何をしてきて今があるのか
・今後何をしていきたいのか
そして同じ素材を自分で集めて、真似して記事を書いてみる。
自分が書いてみたい媒体、テーマやジャンルごとに理想の記事を見つけて「型」を研究しておけば、勉強になる上に、それがそのままライターとして書ける分野を広げることに繋がっていくそうだ。
また江角さんは、小泉今日子さんの書評コラムが好きで、たくさん読んで分析したという。
自分が気に入っている文章や、好きな人が書いたものを使うというのも魅力的!
「書き手」という目線は、とても新鮮だった。
さっそく役に立っていること
インタビュー原稿でかなり大事なのが、締めの言葉。
どんな文章を最後に持ってくるかで書き手の個性が出たり、記事の読後感にも繋がるという。
江角さんは様々な記事の締めだけを読んだり、「言葉ノート」というのを作って、いい締めがあるとメモしているそうだ。
締めや文末に同じ言葉を連発しないために「類義語」を調べることが役に立つと聞いて、ブログなどを書く時にさっそく実践している。
楽しかった、嬉しかった、おもしろかったなどの締めはどうしてもたくさん使いがちだが、インターネットで「おもしろい 類義語」などと検索するといろいろな言葉が出てきておもしろい。いや、心が踊る。
さらに驚いたことがある。
仕事の依頼者から、事前に完成品の参考レイアウトを紙でもらっておき、一行の文字数を確認したり、改行の位置を考えながら原稿を作る配慮も大切だという。
なんと細かい気遣い!
でもこのひと工夫で「おっ、読みやすい原稿を作ってくれるライターだな」と認識されれば、次の仕事にも繋がりやすいと聞いて納得した。
見た目への配慮は、メルマガやブログにも使うべし!ということで、こちらもさっそく自分のブログで試してみた。


ブログをスマホで表示させて、改行した方が良さそうなところを直してみた。
すると見た目もかなりスッキリして、読みやすくなった!
以前、パソコンとスマホでは一行の文字数が違うので、改行してあると逆に読みにくくなる場合があると知り、あえて改行しないでブログを作っていた。
でも実際にスマホに表示させて、それに合わせて改行してみると、パソコンでも読みやすいことがわかった。
なんでも試してみるものだと改めて実感した。
まとめ
人や自分の思いを文章にする、インタビュー原稿。
これが書けるようになれば、あらゆる記事に応用できるという「基礎」を今回は教えていただいた。
「自分がどんな媒体で記事を書いてみたいか?」と思いながら文章を読んだことが今までなかったので、本や雑誌、web媒体の読み方が、今後180度変わりそうだ。
