京都ライター塾第3回目レポート
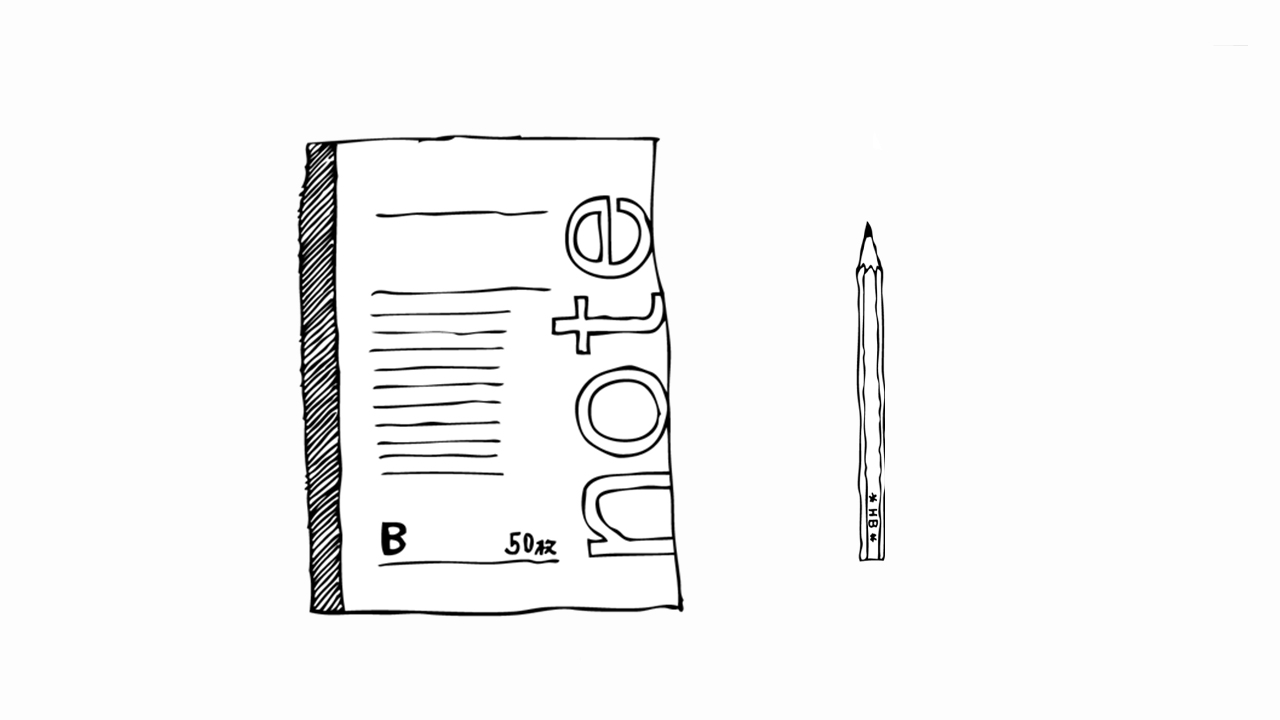
日付:2024年2月10日
江角悠子さん主宰
京都ライター塾の第3回目に出席。
「自分の好きな⚪︎⚪︎」について原稿を書くという前回の課題の添削と、今回の課題につながる「企画の立て方」について勉強した。
受講者全員の添削は内容が盛りだくさん!自分の文章だけでは気づけない書き方のポイントや、読者に伝わるように書くむずかしさも知ることができた。今回も充実の内容だった講座をまとめてみたい。
自分だけが知っている情報を読者に伝えるむずかしさ
まず最初は、前回の課題の添削から。
自分の好きな店や物について紹介した500文字程度の原稿を、江角さんが1つずつ添削してくださった。
専門用語で「朱入れ」と呼ばれる添削。
自分の書いた原稿を作品のように思っていた江角さんは、ライターを初めたばかりの頃、原稿に朱入れされることを人格否定のように感じていたという。しかし経験を重ねるごとに、原稿は読者にわかりやすく書くことが最も大切で、朱入れは文章をより良くするための提案だと考え方が変化したそうだ。
江角さんがどれほど気持ちを込めて原稿を書いていたかがよくわかるエピソード。このような経験談を聞けたおかげで、前向きに添削を聞く心構えができた。
そして始まった朱入れ。原稿の数は10人分!
自分が理想的だと思う記事を見つけてきて分解し、それを真似して書いたものなので、タイトルの付け方や構成も様々。たくさんの文章を読むことで「なるほど!」と思うことが多く、全員分の添削を聞いてメモを取った。書き方のポイントをまとめてみる。
【タイトル】
付け方のコツは、とにかくわかりやすいこと。パッと見て、何のことを説明した記事かわからないようなタイトルはよくない。
例えば私が紹介したのは、ヘッド交換式の歯ブラシ。ヘッドの部分だけを取り替えてハンドルをくり返し使うことで、ごみの量を減らすことができるというものだ。
タイトルは「人にも環境にも優しいエコな歯ブラシ」としたが、これではヘッドを交換するという商品の特徴がまったくわからない。違う方法でエコに貢献している歯ブラシと混同してしまうこともあり得る。
そこで「ヘッド部分だけ取り替える、人にも環境にも優しいエコな歯ブラシ」と特徴を付け加えることを提案された。確かにこれなら商品の具体性がプラスされる。
【本文】
原稿を書く上で大切なのは、とにかく読者に親切なこと。
自分だけが知っている商品や店をどう説明するのか?
使い方やメリットをどう言語化すれば伝わりやすいか?
場所や外観をどう書けば店を見つけやすいか?
読者にとっては何が理解しにくいのか?
書き手の想像力がものを言うと痛感した。
私の原稿で一番の反省ポイントは、タイトルに「人にも優しい」、締めに「からだに優しい」と入れておきながら、どういう点が優しいのかを本文にまったく書いていなかったことだ。
なぜ書かなかったかというと、1ヶ月に1回きちんと交換していつでもブラシが真っ直ぐな状態の歯ブラシを使うことは、虫歯や歯周病予防につながるということを「これは読者も当然理解していることだろう」となんとなく思っていたからだ。書かなくてもわかってもらえるだろうという認識だった。
添削で「からだに優しいとはどういうこと?」と江角さんに聞かれて、説明が足りていないことに気がついた。
何も詳細が書かれていない場合、読者が「もしかして特殊な加工が施された歯ブラシなのか?電動で磨き残しがゼロとかいう画期的な歯ブラシか!?」などと、紹介したい商品とはまったく異なるものを想像しても仕方がない。そもそもインタビュー原稿は、読者が想像しなくてもいいようにズバリと説明する必要があるのに、これでは大変不親切だ。
何がからだに優しいのかを江角さんに説明すると「すごく理解しやすい」と言っていただけて、その必要性に納得できた。
【その他気をつけた方がよいポイント】
・タイトルに「これはどこにでもあるものだ」と読者が思ってしまう言葉を使うと具体性に欠けるので、商品や店独自の特徴を入れること。例えば京都だと、京町家やおばんざいを出す店はたくさんあるのでひと工夫必要。
・1文に情報が盛りだくさんだとわかりにくくなるので、短めにする。
・500文字の中に同じ言葉が入るのはもったいないので、類義語を使うなど工夫して、より具体性のあるわかりやすい文章にする。
・意味が反対になる言葉を並べて書く時は、情報を詳細に書いた方がわかりやすい。例えば「老舗」が「リニューアル」した際は、「場所を移転してリニューアルオープン」など。
・「嬉しい」などの気持ちは書かない方がよい。嬉しいかどうかは読者が決める。
・「寒い夜に」など季節感を入れると冬限定の記事になってしまうので、どの時期でも楽しめるという内容、締めにした方がよい。
・自分の専門分野を説明する時は、専門的になりすぎないように。情報を何も持っていない読者にもわかりやすいように噛み砕いて書く。
インタビュー原稿の読後感として一番大切なのは、この商品を買ってみたい!このお店に行ってみたい!と思ってもらうこと。このゴールを意識しながら、頭の中に映像として思い浮かんでいる商品や店をどう言語化するのか?原稿を書くむずかしさを実践で学ぶことができた課題だった。
企画を立てて仕事を取りに行く!
ライターが仕事を依頼してもらうためには「自分はこんな記事が書けます!仕事があればください!」と、出版社や編集プロダクションにアピールすること、つまり営業が大切。
江角さんがライターを始めた18年前にはクラウドソーシングなどは無かったため、雑誌の裏に載っている出版社に連絡してポートフォリオを見せに行ったり、人脈を広げるために異業種交流会に参加したりしていたそう。
しかし「自分を売り込むことが苦手だった」と話す江角さん。このままでは心が病んでしまうと危機感を抱いたため、自分が書けそうな企画を立てて持ち込むという方法に方向転換したという。
売れっ子と呼ばれるライターは、積極的に企画を持ち込んでいるそうだ。
どんな媒体でも「次の号にはどんな企画を載せるか」ということを常に悩んでいるため、ライターが「こんな記事が書けますがどうですか!?」と企画書を持ち込んで来ることは、鴨がネギ背負ってやって来た状態。仕事を獲得できる可能性はとても高い。
実際江角さんは趣味の読書を活かし、京都を舞台にした本を読んだ感想に加えて、本の中に出てくるスポットについても触れるという書評コラムの企画書を作り、採用につながったそうだ。
このように自分が書きたいテーマを扱っている媒体を探して、持ち込み先を選んでいくわけだが、初心者にとっては「この媒体で書きたい!」とすぐに見つけることはむずかしい。そこでnoteやブログなどにネタを書き溜めながら媒体を探すことが大切だという。
書くことで勉強になるし、だんだんと自分が書けそうな分野も定まってくる。いつか仕事をする時のために準備しておくことは、初心者ができる第一歩と言えるだろう。
狙いを定めて企画を立てる
自分が書きたい記事を、何でもかんでも持ち込めばいいというものではない。実際に掲載してもらえそうな具体的なネタに狙いを定めて企画書を作ることが重要だ。
江角さんが考えるネタの探し方は、
・読者が読みたいもの、知りたいこと
・自分だから書けるテーマ、書きたいこと
・まだその媒体で書かれていないこと
この3点に当てはまるものを見つけること。それはそのまま媒体が求めている企画につながっていくので、採用される可能性も高い。
ここでおもしろい例が挙げられた。
今は引退した大物歌手が、平安神宮近くのマンションに住んでいるという噂があったらしい。もしそれを知ったライターが「元大物歌手のお宅拝見!」と題した企画書を持ち込んだとして、果たして採用されるだろうか?
企画を立てる時には、意識しておかなければいけないポイントがある。
・独自性はあるか?
・具体性はあるか?
・実現可能か?
・話題性はあるか?
これに照らし合わせると、独自性と話題性は抜群。しかし大物歌手がこんな取材を許可するとは到底思えないので、具体性も無いし、実現は不可能だろう。
このように企画書を作る時には、取材を行って本当に記事を完成させることができるのか、具体的に想像してみることが大切なのだ。
話題性は大切だが、大きな企画を考えなくても、ネタは身近にすでに転がっている。自分の悩み、ハマっていることを中心に、1つのテーマを掘り下げてみるといいそうだ。
学生向けなら暗記力、社会人向けならコミュニケーション能力を鍛える方法などに需要がありそうだし、ダイエット記事を書きたいなら実際やってみて、どうやって乗り越えたかを書けば立派な企画ができそうだ。
自分ならどんな企画が立てられるだろうか?
江角さんに「いいね!」と言ってもらえてとても嬉しかった私の趣味、仏像やお寺の企画なら書くのが楽しそうだ。お寺は格式が高そうなので、私なんかが記事を書けるなんて想像もしていなかったが、私だから書けることがあるかもしれないと初めて思えた。何よりいろんな仏像を見に行けると思うと胸が高鳴る!
また社会経験や子育て経験から、自分がこれまで乗り越えてきた悩みについて書くとしたら、具体的な内容を盛り込んで企画を立てられるかもしれない。
こうやって身近なところから企画を考えてみると、なんだか自分でもできそうな気がしてくる。
「むずかしく考えすぎず、頭の体操だと思って!」と何度もアドバイスをくれた江角さん。そんな江角さんにインタビューをする企画書を作るのが今回の課題だ。
講座中は学ぶことがてんこ盛りなので、江角さんとお話できる時間はなかなか無い。仕事と称して、話してみたい人と会えるのがインタビュー企画の醍醐味だそうだが、今回の課題はまさにそれ!
江角さんの魅力を引き出せるように頑張りたい。
まとめ
今回の講座で一番勉強になったのは、自分しか知らないことを、周りにわかりやすく伝える文章を書くことは、とてもむずかしいということだ。記事なら読者に向けて、企画書なら仕事の依頼者に向けて、自分の頭の中にあるものをどう言語化すればいいか、常に考えなければいけない。ライターは、想像力や柔らかい頭を持つことが大切なのだと感じた。
全6回の講座のうち、もう半分が終わってしまった。
京都ライター塾が始まってから、江角さんの「幸せになる」というテーマの中でいろいろな話を聞き、考えていたら、すごく気持ちが前向きになってきた。書くことを中心に回っている生活も楽しい。環境を変えることがこんなに自分にとってプラスになるのか!と驚いている。
江角さん、学びの時間を共有しているみなさんに感謝したい。
そして残りの講座でもたくさんのことを吸収していきたい。
(あと半分で終わってしまうと考えると今からさみしいので、何か書いたりして紛らわせたい。笑)
