京都ライター塾第1回目レポート
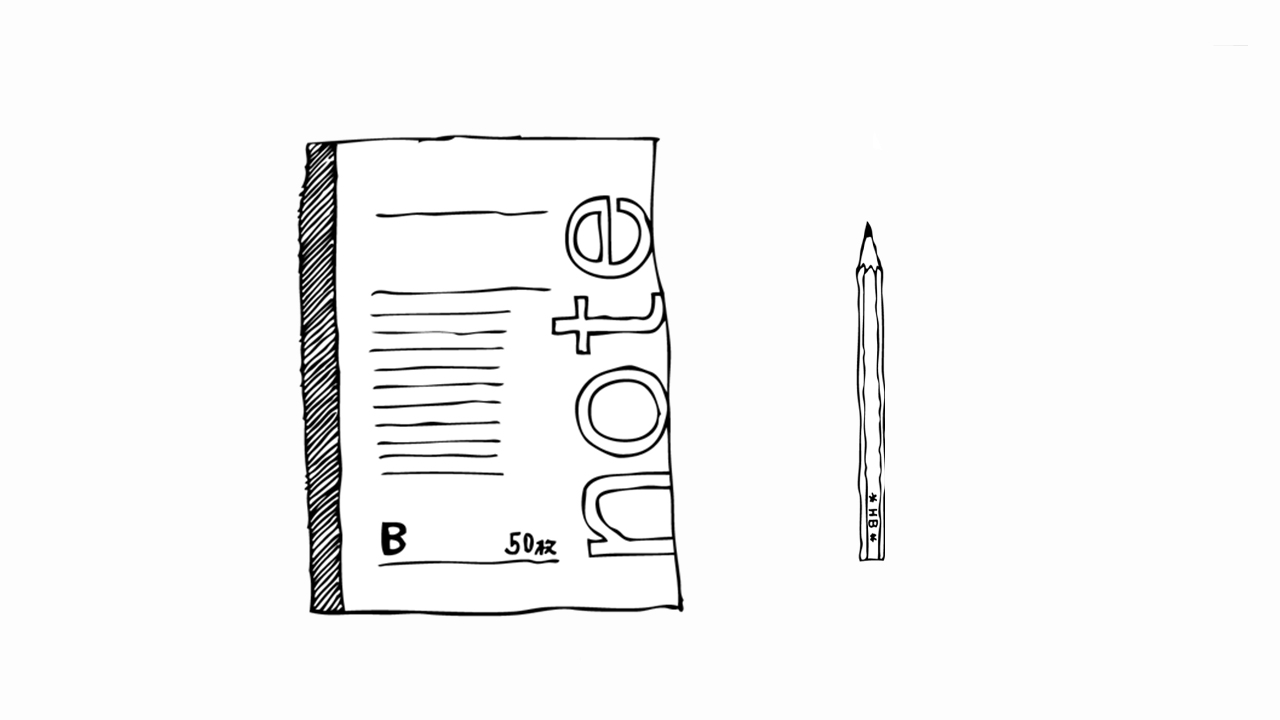
日付:2024年1月13日(土)
京都ライター塾の第1回目に出席した。
今回のテーマは「ライターは何をしているのか?」について。
他己紹介に始まり、商業ライターとしてできる仕事、書けない悩みを解消する考え方、ライターとして活動するならば自分の公式サイトを作るといい、などという内容だった。
その中で分かったこれからの自分の課題、新しい気づきなどをまとめた。
【インタビューについて】
講座の最初に行われたのは、ペアになって5分間お互いにインタビューをし、他己紹介をすることだった。私は人の話を聞くことが好きだし、今後仕事としてインタビューをしてみたいという思いがあるので、緊張しながらもワクワクして臨んだのだが、終わってみて感じたことは、私はインタビューが下手であるということだった。ワクワクだけで成立する仕事では全くないことが分かった。
まず第一の問題は、ペアになって「初めまして。」と挨拶した後、相手との距離を縮めようと思って無意識に世間話につなげてしまったことだ。インタビュー時間は5分しか無いのに、早く本題の質問に入らなければ、本当に聞きたいことにまで到達しない。もしこれが制限時間30分の社長インタビューであった場合、趣味などを褒めてひとしきり楽しく会話しただけで終わってしまっていただろう。想像しただけで震え上がるような大失態だ。
ペアの女性が「じゃあ私から質問しますね。」と言ってくれたおかげで助かった。感謝したい。ちなみに彼女は物腰が柔らかくて話しやすく、質問事項も的確でインタビューが上手だと感じた。
第二の問題は、自分が聞き手の時に、やはりワクワクした話を広げ過ぎてしまったことだ。これは他己紹介が始まってから気づいた。
皆さんの紹介は、現在どのような仕事をしているのか、働きながらどうしてライターに興味を持ったのか、職を変えたいのか副業にしたいのかなど、ライター講座をこれから受けるにあたりとても現実的で具体的なものが並んでいた。
一方私は、ペア女性の地元の話、インスタグラムをしていたことをきっかけに江角さんを知り、ライター塾に参加を決めた話しか聞けなかった。皆さんの他己紹介が進むにつれて、自分の質問内容の薄さに焦りを感じた。
これらの問題点から、私はインタビューについてもっと積極的に学ぶ必要があることが分かった。その場の雰囲気に任せて質問するのではなく、事前に基本的な、絶対にすべき質問事項を把握しておくことや、特に時間配分を勉強する必要があると感じた。
【気持ちにフタをしていることについて】
文章が書けない悩みを解消する考え方を学んでいる中で、無意識に自分の気持ちにフタをしていたことに気づかされた。
これまで私は、お誘いや依頼を受けた際、自分も周りも納得できるような明確な理由が無ければ、お断りすることをしなかった。
「なんとなく嫌だと感じるから、そう伝えたいのだけれど、理由が無ければ伝えにくいなあ。」というレベルではない。「なんとなく」という感覚や理由では、自分が嫌だと感じることさえ許されないと無意識に思っていた。嫌だと感じることにいつも罪悪感を抱いていた。
なぜ私は今断りたいと思っているのかについてとことん突き詰めて考え、理由をこねくり回して悩んでいたのである。そして理由が明確に無い場合は、何か得るものがあるはずだとできるだけ前向きに捉えて、引き受けていた。
ところがこの状態こそが、自分の感情にフタをしている、ということだった。江角さんが「嫌だと思うことに理由なんていらないんですよ。」と言った瞬間「えっ!!!!!!」となって、天地がひっくり返った。まさに、そういう発想は無かった。。。であった。
40年も生きてきて、そのことに思い至らなかった自分に驚愕した。
「なんとなく」こそが大事。
つまりドラマでしか見たことのないようなシーンみたいに、「どうして嫌なの?」と聞き返されて「うーん、なんとなくね。」なんてサッパリと軽く答えてもいいし、思ってもいいということだ。なんて心が楽になる生き方だろう!
じつは今、断るための明確な理由が無くて引き受けそうになっていたまさに「なんとなく」嫌な案件を抱えていたところだったので、講座中にそのことを述べた時、江角さんが放った言葉が爽快だった。
「断っていいんですよお。断ってください。(言い切る笑)」
その言葉に後押しされ、講座終了後1分以内に、適当な理由をつけて丁重にお断りの連絡を入れた!
ああもう悩まなくていいんだと、本当に心が軽くなった。
こういう自分の気持ちや五感にフタをしていることはまだまだありそうなので、自分の主観で文章を書くために、そして幸せに生きるために、フタを開けていくことが重要だと感じた。
第一回目の講座からかなり大きな気づきを得ることができ、大変勉強になってありがたかった。次回も楽しみだ。
